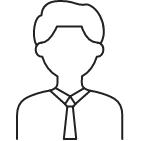弱視の研究者本間律子さん(52、青梅市)が、このほど障害がありながら社会に貢献した人物に贈られる「第19回片岡好亀賞」と「第18回塙保己一賞大賞」を立て続けに受賞した。研究対象を視覚障害者の歴史に絞り、日本の障害者福祉基盤を作った岩橋武夫や盲人専用老人ホームをテーマに多数の論文や著書を発表してきたことなどが評価された。
本間さんはメラニン色素欠乏症の弱視として生まれ、見えないハンデを抱えながらも聖カタリナ女子大学(現聖カタリナ大学)で福祉を学んだ。社会福祉士の資格を取得後、大学のあった愛媛県松山市の障害者計画策定チームに参加。多くの障害者が就労・社会参加を求めているにもかかわらず環境的・社会的要因から実現しない現状を知り、自身が学びを深めることで開ける道があるのではないかと研究者を志した。
一貫して歴史研究を行う理由は、社会の中で盲者がどのような扱いをされてきたかという歴史的な裏付けがなければ実効性のある政策提言には結びつかないとの考えから。「社会に認められるには研究者として大成する必要がある」と必死で勉強し、結婚・出産を経て進んだ関西学院大学大学院で、最短の3年で博士号を取得した。
その後取り組んだ盲人専用老人ホームの研究が縁で聖明福祉協会(青梅市根ヶ布)の本間昭雄会長(96)と出会い、2016年、聖明園入職と同時に会長の養子に。現在は会長秘書兼生活相談員として勤務する。
価値ある2つの賞を受賞した次の目標は本間会長の伝記を書くことという。「本間昭雄は日本で初めて軽費の盲老人ホームを開設し、全国に広めた人物。伝記を通して盲老人ホームの必要性を社会に認めてもらえたら」
肌や髪の色素が薄く光をまぶしがる幼い本間さんを診て、国立病院の医師は「この子は20歳まで生きられないかもしれない」と両親に告げた。両親は本間さんの3人のきょうだいに「もし20歳以上生きた場合は皆で支えてほしい」と経済的な支援を要請。実際その必要はなかったが、「おかげでみんな手堅い仕事に就いた」と笑う。
義父の本間昭雄は医療事故により20歳で失明、26歳で現在の事業を始め、「失明したからこそ一生を貫く仕事が得られた。失明に感謝」と朗らかに言う。その域には達しないまでも、「私も視覚障害者でなければ研究者にはなっていなかった」。稀有な境遇をしなやかに受け入れ生きていく。


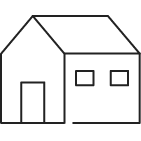 住んでみたい
住んでみたい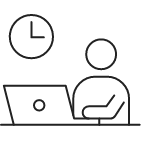 働いてみたい
働いてみたい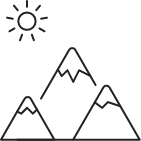 遊びに行きたい
遊びに行きたい